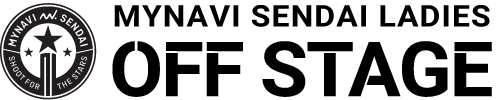「どんな道も自分で選び、突き進んできた。課題と向き合う芯の強さを持って」
14 MF 茨木美都葉選手
マイナビ仙台レディースの選手に、これまでの歩みを振り返ってもらう「マイヒストリー」。それぞれのサッカー人生に物語があり、かけがえのない記憶があります。今回は14MF茨木美都葉選手にお話を伺いました。膝の大けを乗り越えて、今はつらつとプレーしている茨木選手。どんな時も自分と向き合いながら、課題を克服してきました。これまでの歩みについて伺っています。
「男の子に負けたくない。サッカーが上手くなりたい」小さい頃から負けず嫌いの性格。
――茨木選手は熊本県出身。小さい頃はどんなお子さんでしたか?
「たくさん習い事をしていました。ピアノ、体操、水泳もしていました。幼稚園の頃にドラム教室にも行きましたし、英語も習いました。3姉妹なんですが姉たちがバドミントンをしていたのでその練習について行ったりもしました。友達とは野球をして遊んでいました。いろんなスポーツに触れて遊んでいました。自分でやりたいと言ったのはサッカーと水泳でしたね」
――サッカーを始めたのはいつでした?
「4歳の時で、熊本のテレビ局のイベントに参加したことがきっかけでした。テレビ局を見学し、外の広場で『幼稚園生のサッカー大会』がありました。それを見て『あれをやりたい!』と参加させてもらいました。当時通っていた幼稚園でもサッカー教室があったので、そこから初めて、今までずっとサッカーをしているという状態です」
――どこにきっかけがあるかわかりませんね。そこからプロサッカー選手への道がつながっていたという……。どんな環境だったのですか?
「幼稚園から小学校までは、ずっと男子の中で女子は私一人でした。小学校は熊本市にあるクラブチームでプレーしました」
――どんなところにサッカーの楽しさを感じていましたか?
「小学生の時は、とにかく男子に負けたくない。上手くなりたいという思いですね」
――中学年代からJFAアカデミー福島へ入りましたが、どのような経緯があったのでしょうか?
「熊本県でサッカーを続けられる環境がなく、当時スキルアップのために通っていたクーバー・コーチングというスクールで親が相談したところ、JFAアカデミー福島を勧められました。『力試しに受けてみるか!』という感じで応募してみました」
――力試しだったのですか?
「はい。小学校6年生の夏あたりから、一次試験、二次試験、三次試験と進んで行きました。受かると思って受けていなかったので、親元を離れるということも考えていなかったです。まさか合格すると思っていなかったので……。楽しみだし、嬉しかったことを覚えています」

JFAアカデミー福島で育んだ「課題と向き合う力」
――実際に入学してみてどんな日々を過ごしていましたか?
「入学する年は2011年、3月に東日本大震災が発生しました。最初は福島に行くつもりで、中学校の制服も頼んでいたんですが……。3月の最後に、一度東京のJISS(国立スポーツセンター)に集まり、静岡に行くということになりました。バタバタしていましたね。『御殿場ってどういう字を書くんだ?』というくらい……。そこから始まりました。通うことになった中学校の名前も周りの人に聞いたぐらいです(笑)」
――その段階でまだ中学1年生ですもんね。JFAアカデミーの仲間、同期は何人いましたか?
「7人です。今はみんな海外にいますね。スタンボ―華(NWSL、エンジェル・シティーFC)や平田舞(スイス、バーゼルFC)、スペインに大熊良奈がいて、引退した選手もいますがそれぞれがんばっています」
――静岡で始まったJFAアカデミー福島での生活。生活環境もプレー環境も大きく変わりました。
「ホームシックになる暇がないくらい、1日のスケジュールがパンパンで忙しいんです。毎日、ホワイトボードに書かれたスケジュールに追われていたという感じです。寮生活は楽しかったです。みんな『サッカーが上手くなりたい』と集まってきた人たちだし、実際に上手い人だらけで、意識も高い。大変なことはあったかもしれないですけど、今振り返ると楽しかったですね。アカデミーに行って良かったです」
――この6年間で一番磨くことができたのはどのようなことでしたか?
「課題に対しての取り組み方です。3か月に1回、自分のサッカーの課題について、考えて発表する機会がありました。課題としていることについて、自分の映像とプロ選手の映像、そして3か月間取り組んできた自分の映像を比較し、どういうことをしなければいけないのか、どういうことに取り組んできたのか?ということを5分間で発表するんです。そういうことを通して課題に向き合ってきた経験は今にもつながっていると思います」
――須永純監督は「JFAアカデミー時代から茨木選手のことを知っている」という話もされていました。
「須永さんは当時、JFAアカデミーで男子のGKコーチを務めていました。久しぶりに仙台で再会した時に『大きくなったなぁ』と言ってもらいました(笑)びっくりしました。JFAアカデミーは男女で同じ食堂を使うんです。毎日男子の寮に歩いて行ってご飯を食べ、女子の寮に戻るという生活だったので、男子のスタッフと顔を合わせる機会も多かったです。須永さんは女子の試合もよく見てくれました」

クラスメートはアスリートだらけの日体大。卒業時にWEリーグが誕生。
――この6年間を経て、日本体育大学へ進学しました。
「高校卒業時に家族で話し合って、『大学に入った方が良いよね』という話になりました。日体大はなでしこリーグにも参戦していること。インカレで最多優勝してることなども選んだ要素でした。また教員免許も取ることができるし、アカデミーの先輩もいたので、日体大へ練習参加しました。部のきまりも厳しいとは聞いていたのですが、それもいいかなと思いました」
――大学4年間はいかがでしたか?
「2年生と3年生の時にインカレで優勝しました。行って良かったと思っています。他競技の学生も、インカレで優勝していたり、オリンピックに出ていたりという環境。学生だけではなく、教授もそういう方々ばかりで、アスリートに囲まれた4年間でした。ラグビーの大竹風美子選手は今でも仲良しです。その他にもクラスメートにはパラリンピック水泳の選手やゴルフ、スピードスケート、フィギュアスケート、アーチェリーの選手もいました」
――茨木選手は4年生でキャプテンも経験されていますね。
「日体大はインカレで優勝するということが1年間の最大の使命なんです。日体大の歴史を継承していくために厳しくなければいけない。誰でもできるわけではない経験でした。周りは私のことをすごく厳しいと思っていたのではないかと……」
――誰よりも自分自身に厳しい、ストイックなイメージがあります。大学卒業は2021年、ちょうど秋からWEリーグがスタートするタイミングでした。
「大学卒業前の1月末にアルビレックス新潟レディースに入ることが決まって、2月からチームに入りました。最初は働きながら、トレーニングを行っていました」
――新潟Lでの1シーズンはどのような期間でしたか?
「けが明けのタイミングだったので最初は大変でしたが、試合にも多く絡ませてもらいました。川村優理さんや上尾野辺めぐみさんなど、長年在籍している選手も多かったです。“アルビの色”というものが強くあると感じていました。男子も女子もサポーターの皆さんが熱かったです。大学時代は、応援はありましたが、ファンの方がいるという環境ではなかったです。コロナ禍でしたが、応援がすごい。嬉しいなと感じていました」

けがに長く向き合った仙台での日々。自分で選び取った道を歩む。
――2022-23シーズンにマイナビ仙台レディースへ移籍し、3季目を過ごしています。2023年7月に前十字靭帯を損傷し、けがとの長い戦いがありました。復活した今はどのように過ごしていますか?
「課題だらけですよ。自分の映像やプレーを振り返ることができるというのは、『ピッチに戻ったな』『これが自分の日常だったな』と実感しています。課題を克服して進んできたと思っているので、自分の課題に取り組み、まだまだ成長できると思いながら日常を過ごせるのは特別ですね」
――チームとしてはなかなか結果が出ない苦しい時間が続いています。勝てない時にいかに課題と向き合っていくかというところは、これまでの経験も生きる部分なのではないですか?
「勝ちながら自分に向き合う。勝ちながらチームとして修正していければ良いですよね。そう願っているのですが……。負けて反省していくというのは、選手もスタッフも苦しいです。まずは試合に絡みたい。チームが勝ちに向かっていく、その中で何かをしたい。これまでリハビリ中は、外から見ているしかなかった。中でサッカーをやれるということは、幸せなことでもあるんです。けがをしたからそう思うのかもしれないです。勝たなければいけない世界なので、サッカーができて幸せとか言っている場合ではないんですが。自分の感情としてそれは置いておいて、プロは結果にこだわらなければいけないと思っています」
――今後の目標を聞かせてください。
「けがをせずに1シーズンやり切ることです。新潟Lでは(川村)優理さんは前十字靭帯を3回切っているし、武田あすみ選手もけがをしていた。同じけがをした2人にたくさん支えられました。他にも家族やチームメート、友達、ファンなど大切な人たちから助けられて踏みとどまって、食いしばってがんばってきたので、そういう人たちに結果で伝えられるようにしたいです」
――そう考えると復帰戦の皇后杯5回戦、セレッソ大阪ヤンマーレディース戦のゴールは本当に素晴らしい成果でした。
「あんなことはもうないですよ。復帰戦でゴールを取るなんて思ってもみないです。映像で残っているので……。ゴールを決めてみんなが寄ってきてくれるんです。ゴールを決めたことよりも、多くの方が喜んでくれたということで、決めて良かったと思いました」
――サッカーをしている子どもたちへアドバイスを頂けますか?
「進路のことで考えると、いろいろな情報を集めてみたり、話を聞いたりした上で、自分が何を大事にするか。『その環境を自分で選んだんだから』と思える場所を見つけられるかだと思います。誰かに勧められたままでは、上手くいかない時に誰かのせいにしてしまう。私は自分で受験し、自分で決めた。自分で教員免許を取ろうと思いました。進学した先でやりたいことを見つけてここまでこれたので、“自分で”ということが大事なんじゃないかなと思います。自分で何を学びたいか、何をしたいか。『誰かと一緒だから』ではなく、誰も知らないところでも、『これを学びたい。ここで生き残ってやる』という気持ちが大事なのかもしれません」

文・写真=村林いづみ